2024年10月25日、フランス・ソジョンにて「バーンアウト(燃え尽き症候群)」をテーマとした円卓会議が開催されました。複数の専門家が集い、この重要なテーマについて意見を交わしました。本稿では、その会議の内容を美容・ウェルネス業界向けにまとめてご紹介いたします。
執筆:Doriane FRÈRE
当日の会場(定員600名)はほぼ満席となり、10月の夜、数多くの専門家たちがステージに登壇し、現代の職場において深刻な課題となっている「バーンアウト」について議論を行いました。出席者は以下のとおりです。
Dr. Patrick Légeron:職場のメンタルヘルスに関する精神科医で、パリのSainte-Anne病院に所属していた経歴を持ち、フランス医学アカデミーに提出されたバーンアウトに関する報告書の共同執筆者。Sciences-Po Paris講師。
Benoît de Saint-Aubin:Avelvat Consulting創設者であり、かつてOrangeグループの幹部として戦略・組織改革の実務経験を有するコンサルタント。
Dr. Catherine Badinier:行動療法および認知行動療法の心理療法士であり、CAC 40グループに所属する企業の産業医。
Philippe Guillard:かつて企業の上級幹部として働き、バーンアウトを経験した当事者であり、著述家。
Corinne Imbert:薬学博士で薬局経営者。シャラント=マリティーム県選出の上院議員として社会問題委員会の書記を務め、社会保障評価・監視ミッションにも参加。
Dr. Olivier Dubois:精神科医・温泉療法医。ソジョンのクリニックおよび温泉施設の代表であり、「ストレス温泉学校」の創設者。ストレスや温泉医学に関する複数の著書・研究論文を執筆。
バーンアウトの起源
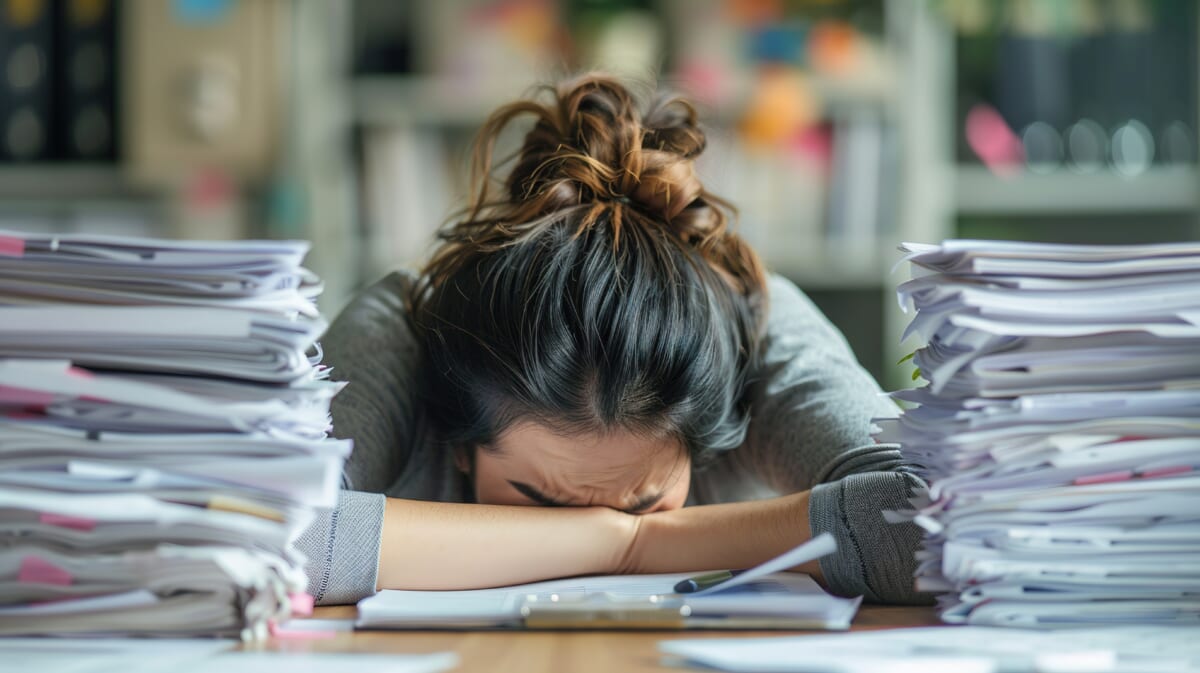
冒頭ではDr. Légeronがバーンアウトの基本的な定義について説明しました。多くの人が誤解しがちですが、バーンアウトは新しい病気ではありません。古くから存在するものであり、その兆候は旧約聖書にも記されています。
「列王記」には、預言者エリヤが善なる言葉を広めようとして疲弊しきった状態、いわゆる「預言者エリヤの大いなる疲弊」が描かれています。この記述には、現代でいうバーンアウトと類似した症状が見られます。Dr. Légeronによれば、「うつ病などの他の精神疾患と同様に、いわゆる現代病とされているものの多くは、実は昔から存在していました」とのことです。また、ホメロスの『イーリアス』にも、戦士たちがうつ状態にある様子が描かれており、現代の精神科医が診断するような症状がすでに記されているといいます。
バーンアウトという概念が医療的に注目されたのは1970年代に入ってからです。アメリカの精神科医Herbert Freudenbergerが薬物依存症患者を治療する中で、医療従事者たちが次々と極度の疲弊状態に陥ることに気づき、これを「バーンアウト」と名付けました。彼は、この状態が特に熱心に働く人々に多く見られることから、「闘う人々の病」とも呼びました。
1980年代には、心理社会学者Christina Maslachが以下のように定義しました。「バーンアウトとは、感情的疲弊、人格の喪失、そして業務効率の低下を特徴とする状態であり、他者と関わる仕事をしている人に発症しやすい」
バーンアウトの症状

Dr. Légeronによると、バーンアウトには大きく3つの主な症状があります。
- 極度の疲労:体力・気力が枯渇し、服を着替えるような些細な動作ですら困難になります。集中力の著しい低下も見られます。
- 感情の喪失:感情をまったく感じられなくなります。喜びや悲しみといった感覚も鈍麻します。
- 自己評価の低下:仕事において自分が無価値だと感じるようになります。うつ病にも似ていますが、うつ病が家庭生活など広範な影響を及ぼすのに対し、バーンアウトは主に職場での自己認識に関係します。
バーンアウトは、もともと一時的なストレス(例:締切のある案件、同僚との口論など)が慢性化した結果として発生します。これを「過剰ストレス(ハイパーストレス)」と呼び、バーンアウトはその最終段階と位置づけられます。
ただし、複数の専門家が問題提起したのは、この深刻な状態がいまだ国際的な病気分類に認められていない点です。世界保健機関(WHO)は2019年、バーンアウトを疾病リストに追加することを拒否しました。Dr. Légeronは「これは単に“仕事に関連する状態”とされているだけです」と落胆をにじませました。
回復に5年かかった重度バーンアウトの現実
「今では運転もできず、仕事も続けられません」――Philippe Guillard氏の証言が語るバーンアウトの深刻さ
バーンアウトがいかに深刻な影響を及ぼすかを、Philippe Guillard氏の証言は如実に物語っています。5年前、52歳のときにバーンアウトに陥ったといいます。
「私は大規模な公共機関に勤務し、経営陣の一員として取締役を務めていました。また、鉄道会社の社長も兼務しており、極めて多忙で責任の重い業務に携わっていました。仕事には非常に熱心に取り組んでいました」と彼は当時を振り返ります。
予兆の現れ
バーンアウトが発症する約2年前、Guillard氏はすでにいくつかの兆候を感じ取っていました。「自分の仕事に意味を見いだせなくなっていたのです」と語り、次第に業務の世界が「作為的で、不誠実さに満ちた環境」へと変わっていったと明かします。
バーンアウトが急速に進行したのは、勤務先の社長から受けたハラスメントがきっかけでした。「非常に強いストレスを感じていました。ハラスメントによってうつ状態に陥り、ついには休職せざるを得ませんでした。しかし、休職後も嫌がらせは続いたのです」と元幹部のGuillard氏は続けます。
転機となった朝
ある朝、Guillard氏は突然体に力が入らず、指一本動かすことができなくなりました。何の感情も湧かず、しばらくの間、そのままの状態が続いたといいます。「とても激しく、そして突然のことでした。まるで内側から全てが焼き尽くされたような感覚です。記憶はずたずたに引き裂かれ、5年経った今も人生の一部の記憶が失われたままです。最も辛かったのは、消費したエネルギーを補う力が一切なくなったことです。人と会話する気力も、思考する力も残っていませんでした」
5年後の今でも続く影響
現在、Guillard氏が自立して過ごせるのは、1日に3時間程度。しかも、過度な負荷がかからないことが前提です。運転もできず、仕事に復帰することも叶いません。「人生が断絶されたように感じています」と語り、集中できる時間を使って執筆活動を行っています。
幸いにも、Guillard氏のケースは「職業性疾患」として認定されました。バーンアウト自体は疾病として分類されていないにもかかわらず、です。「裁判を通じて、元の勤務先に重大な過失があったことを認めさせることができました」と結びました。
バーンアウトは予防こそが鍵

2024年10月25日、フランス・ソジョンにて開催された「バーンアウト」をテーマとした円卓会議の様子
バーンアウトは深刻な疾患であり、医療的な対応と適切なケアが必要です。Dr. Patrick Légeronは次のように語っています。「講じるべき最も重要な対策は、ただ一つ―それは予防です。特に医療従事者にとって、バーンアウトを未然に防ぐことは最優先事項であるべきです」
自らが最初に気づくべき兆候
Dr. Catherine Badinierは、バーンアウトの兆候に気づくことの重要性を強調しました。例えば、湿疹が出やすくなる、頻繁に体調を崩す、高血圧を発症する、帯状疱疹を患うなど、身体的な異変がサインとして現れる場合があるといいます。
さらに、慢性的な疲労感、不眠、イライラしやすくなる、集中力が低下するなどもバーンアウトの前兆に含まれるとのことです。加えて、周囲の人々――特に家族や同僚――が気づく、気分や言動の変化も、早期発見の鍵になるとしています。
企業に求められる役割
企業においても同様に、細やかな観察が求められます。「仕事が非常にできる人こそ、注意が必要です。そのような人には『何か困っていることはないか』『助けが必要ではないか』と、声をかけることが大切です」とDr. Badinierは述べています。
彼女によれば、バーンアウトの兆候は極めて見えにくく、実に140通りもの臨床的な現れ方があるとのことです。そうした兆候を見逃さないためには、企業が率先して社員の状態に関心を持ち、気づく姿勢を持つことが不可欠です。特にマネージャーの立場にある人たちは、日々のコミュニケーションを通じて、部下がどのような状況にあるのかを把握する努力が必要だと訴えます。
産業医の役割とは
大手企業で産業医を務めるDr. Badinierは、社員に対して「私の診察室では安心して話してください」と常に伝えているといいます。「多くの場合、そこで初めて社員が自分の限界を打ち明けてくれます。私はその話を聞きながら、過度な仕事への傾倒がどの段階にあるのかを見極めるのです。重要なのは、ある日突然、職場から姿を消してしまう“断絶”を回避することです」と強調しました。
バーンアウトを防ぐための組織改革と現場支援の要点
Benoît de Saint-Aubin氏は、現在の職場環境について「従業員の不調を助長する要因が、今やすべて揃ってしまっている」と指摘します。「気候変動、武力紛争など不確実な情勢が続くなかで、消費者の期待も変わり、企業で働く従業員の価値観も変化しています。多くの人が、自分の仕事に“意味”を求めているのです。こうした様々な要素が重なり、バーンアウトは今や爆発的な問題となっています」
こうした背景を踏まえ、Saint-Aubin氏は「私たちは“仕事の再編成”の夜明けに立っている」と表現します。企業は社員との関係を見直し、働き方を柔軟に変え、従業員の貢献をきちんと認める仕組みを築いていかなければならないと述べました。
顧客対応の現場で進むストレスの悪化
Benoît de Saint-Aubin氏は、顧客と接する職種において「無礼な振る舞い」が増加していると指摘します。これが従業員のストレス全体を押し上げているのです。
マネージャーの役割は極めて重要ですが、組織内で「業績の達成」と「部下のケア」という相反する期待の板挟みにあるとされます。そのため、「綱渡り」のようなバランス感覚が求められるのです。
パフォーマンスと職場の幸福をどう両立するか
Saint-Aubin氏は続けます。「現在、多くの企業が、職場の生活の質が重要であることにようやく気づき始めています。精神的健康についての啓発は可能ですが、これは複雑なテーマです。だからこそ、職場のQOL(生活の質)に関する体系的な方針を整えることが不可欠なのです」
「業務量、業務の強度、人間関係など、こうした点について語ることは非常に重要です」と彼は強調します。
企業が講じるべき具体策とは
企業がバーンアウトに対応するには、複数の施策が考えられます。Saint-Aubin氏は以下のような方針を提案します。
社員の声を聞くこと
そのために有効なのが、社員の実態把握を目的とした社内調査の実施です。たとえば、「自分の会社に誇りを感じているか」「職場環境に満足しているか」「他人に自社を勧めたいと思うか」などの質問を通じて、職場の本質的な評価を明らかにすることが可能です。
小さな兆候への感度を高める啓発活動
「職場のウェルビーイングに関する取り組みを導入した企業では、社員のエンゲージメント(仕事への積極的な関与)率が大きく向上しています」と、同氏は述べています。
フランスにおける、バーンアウトをめぐる法整備と課題
Corinne Imbert上院議員によれば、「フランスでは“バーンアウト”という言葉自体が乱用されているため、職業病としての認知が遅れている」とのことです。
しかし、1993年には、ある症状が職業病として認定される制度が整備され、2015年には精神疾患も職業病の枠組みに含まれるようになりました。これにより、バーンアウトについても法律的な対応が進められてきたのです。
ただし、バーンアウトは現時点で明確に「職業病」として分類されているわけではありません。とはいえ、フランスの社会保障制度においてはその治療がカバーされているのが実情です。
Imbert氏によれば、「社会保障制度には5つの柱があります。URSSAFによる『徴収部門』、児童手当などを担う『家族部門』、医療・職業上のリスクに関する『健康保険部門』(年間予算は2,600億ユーロ)、さらに『年金部門』と『介護部門』があり、総予算は6,600億ユーロを超えます。企業に対して過失を問う法的手続きを経ることで、バーンアウト治療に対する補償が得られる仕組みです」と説明しています。
ストレスからの回復を促す温泉療法という選択肢
バーンアウトの治療は、まずは休職による休息が基本です。うつ症状を伴う場合は、抗うつ薬の処方が行われることもあります。
一方で、薬物療法に代わる選択肢として注目されているのが「温泉療法」です。患者が日常から離れ、環境を大きく変えることができるため、高い効果が期待できます。なかでも、Dr. Olivier Duboisが所長を務めるソジョンの温泉施設は、バーンアウト治療の分野において高い評価を得ており、国内でも代表的な医療温泉施設として知られています。
